![]() ゆうが語る、フォークロア
ゆうが語る、フォークロア![]()

![]()
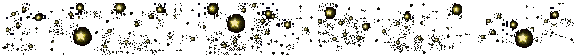
今でこそ「金縛り」に対して恐れることはなくなりましたが・・・、若い頃はその物理的な
苦しさのために一時、夜、床につくのが恐怖以外何者でもない時がありました。
なにしろ一晩で30回以上も、繰り返し金縛りに遭うことなど当時の私にとって
なんら珍しいことではなかったからです。しかも・・・・・。![]()
![]()
![]()
ただ金縛りに遭うだけではなく、この世のもとは思えない異形のなにかが
苦痛を伴って、私を苦しめました。今思えば、よく精神がおかしくならなかったものだと
我ながら自分の精神力を褒めてやりたいぐらいです。![]()
![]()
そんな毎日でしたが、私は元気よく暮らし、青春を謳歌していたのですから。
これはその時の一つのエピソードです。![]()
ある晩のこと・・・。私は激しく金属の触れ合う音で目を覚ましました。目を覚ますと![]()
習慣で時計を見る癖がありますが、まもなく明け方になろうとする午前4時過ぎでした。
ベッドに寝ていた私は、時間を確認した後、何気なく部屋を見渡すと・・・・。
ぼろぼろの着物をまとい、月代(さかやき)の伸びた浪人風の侍が二人、![]()
私の部屋の中で、なんと切り合いをしているではありませんか。![]()
![]()
驚いた途端、金縛りになりました。私はまったく身動きができませんでしたが、
幸いなことに、彼らは私には気づいてはいないようでした。![]()
侍は何かを互いに口走りながら、7畳ばかりの洋間で死闘を繰り広げています。![]()
部屋の中には描きかけの油絵が何枚か立てかけてありましたが、彼らは
それらを巧みによけながら、間合いを詰めては切り結び、また、飛びのくということを
繰り返していました。![]()
![]()
そのうちに片方の侍が、気合声と共に相手を袈裟がけに切り付けた・・と
真っ赤な血しぶきが部屋の中に飛び散りました。
壁一面は、切られた侍の血で染まっています。私はそれを見て気を失いました。
翌日・・・・。![]()
![]()
いつもと変わらない、穏やかな朝を迎えて私はあれは夢だったのだろうかと
ぼんやりと考えていましたが、あっと声を上げて飛び起きました。
血しぶきで染まったかもしれない壁には、私の大切な額がかけてあったからです。
とりあえず、壁をみると何も変わることはありませんでした。が、額を外してケースから
出して調べて見て私は愕然としました。額の中身には、霧を吹いたように
薄いピンクとも茶色ともつかない染みがついていたのです。![]()
![]()
その染みは・・・・、昨日まではなかったものでした。![]()
![]()
あの侍は、一体・・・・・。なにゆえ切り合っていたのでしょう?
大切にしていた額を、私はそれからしばらくして涙を飲んで捨てました。
やはり、気持ちが悪かったし、不吉な感じがしたからです。
![]() それではまたおあいしましょう・・・。
それではまたおあいしましょう・・・。![]()

![]()
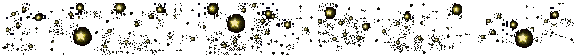
これは数年前、私が珍しく38度の熱を出して寝込んでいた時に体験したことです。
平熱が35度そこそこの私にとって、これは大変苦しいものでした。医者でもらった
頓服薬もまったく効かず、私は仕事もキャンセルして寝ていました。
熱を出して3日目のこと・・・。夜の7時半頃のことです。私は熱を測ろうと思って、
目をつぶったまま枕元においてある体温計を手探りで取ろうと手を伸ばしました。
すると、私の手に触れたのは体温計ではなく温かい人の足でした。「・・・・?」
目を開けて手に触れたものを見ると・・。
それは正座して座っている亡くなった母の下半身でした。![]()
見覚えのあるスカートをはいた、母の腰から下だけの姿だったのです。
そして、腕だけが私の髪を優しくなでるように私の頬の辺りに見えました。
「おかあさん・・・」私は母に話し掛けながらふっくらとしたその手にそっと触れました。
母の手を握った私は何故かとても心が安らいで、熱があるのにもかかわらず大変
気持ち良く、このまま眠ってしまいたいとも思いましたが、もし眠ってしまったら再び母の
姿を見ることはできないだろうと思い、どうしたものだろうかとしばらく考えていました。
そうしているうちに、ふとまったく馬鹿げた考えが浮かんだのです。![]()
『自分が身体から抜けて魂だけになってしまえばお母さんにあえる・・・。』
それに熱があるのだから、そうした条件は整っているような気がしました。
母の手を握りながら目をつぶった私は、たちまちなにか吸い込まれるような感覚の中で
意識だけがひょいと身体から抜けたような気がしたと思ったら、
私は枕元に立っていたのです。
同時にさっきまでの熱の苦しみが嘘のように楽になっていました。![]()
私は鏡に自分を映してみましたが、鏡に自分の姿は映ってはいませんでした。
さらに自分の手を調べてみると、私の手は白い光のようなもので覆われているのが
わかりました。
「おかあさん?」私は母を呼びながらリビングまで歩いていき、母を探しました。![]()
すると、キッチンに母が見慣れない中年の白衣を着た男性を伴って座っていました。
この人は、どなた?私が母に尋ねると、母はにこにこして答えました。
「ゆきちゃんがなかなか良くならないから、こっちでやっと探して来てもらったのに
どうにもならなくて困っていたんだよ」![]()
![]()
母の声は、「聞こえる」というよりも、私の心に響いてくるような感じです。
私が戸惑っていると、いいから診てもらいなさいというように母が私をその男性に
娘なんですよと言いながら、紹介しているのには笑ってしまいました。
その人は、この人は生きている人だからなぁ・・と言いながら
持ってきた黒いかばんの中から細い注射器を取り出して私の腕に注射をしたのです。
それは、あっという間でした。![]()
死人から食べ物をもらう夢は良くないことの前触れだと言うが、これはどうなんだろう・・
呆然としてそんなことを考えているうちに、
私はひどく咽喉が渇いているのに気がつきました。テーブルの上の飲みかけの
アイスコーヒーを手に取ろうとしましたがコップがつかめません。
それを見ていた母は私に、もう帰るからと言って目の前から消えてしまいました。![]()
私はどうにも仕様がなく、自分はまだ生きているのだから自分の身体から出たものは
元に戻れるだろうと思っているうちに意識を失いました。
気がつくと再び布団の中でした。
随分時間が経ったようでしたが、ほんの5分ほどの出来事でした。
そして、さっきまでの熱が嘘のように引いてからだが楽になっていたのです。
翌日から私は起きられました。![]()
![]()
あの、母が連れてきた男性のお医者さんについて、その後ずっと考えていましたが
やっと思い出しました。実家の近くにある医院のお医者さんで、私が幼い頃何回か診て
もらったことのある人だったことを。
そのお医者さんは心臓麻痺で随分前に亡くなったことも聞きました。
たとえ夢であれ、亡くなっても私を気にかけてくれていた母の愛情を胸に感じます。
それではまたおあいしましょう・・・。

さて、ここで皆さんにも一休みして頂きましょう。 ![]()
私がここでお話するのは、「幽霊」を初めて見た時のことです。思えば、これが私の
あの世の人々に対する価値観を作ったともいえる、いわゆる「原体験」なわけですから、
その体験はある意味ではとても幸せだったのかも知れません。![]()
![]()
今でもはっきりと覚えていますが、それは、私が3歳になる数日前のことでした。![]()
私の記憶は、悲しんでいる母に連れていかれた、母の実家から始まります。
開け放たれた玄関を入ると部屋の中は沢山の花であふれていました。
部屋の隅には箱があり、いろいろな人がかわるがわるその箱を覗いては泣いています。
誰かが、おばあちゃんが死んじゃったと言っています。![]()
人の死を理解するのには、あまりにも幼かった私はその意味が分かりません。
私が母にどうして泣いているの?と聞くと母は、おばあちゃんがいなくなっちゃった・・
というのです。私は不思議でした。 ![]()
![]()
不思議という言葉を当時は知らなかったと思いますが、だって部屋の中には、![]()
ちゃんとおばあちゃんが座ってにこにこ笑っていたからです。
棺の中の祖母は確かに目をつむって寝ています。
しかし、祖母は私に優しい笑顔をむけて、ちゃんとそこに座っているのに・・
誰も祖母の方を見ようとはしないのが不思議でした。 ![]()
そして私は・・・「あそこにおばあちゃんがいる」と言って叱られた記憶があります。![]()
祖母はその後、私が小学校の4年生になるまで、母の実家に遊びに行くたびに
笑顔で迎えてくれました。ある時、法事の席で叔母が青ざめた顔で親戚の人に
小さな声で話しているのを聞きました。
「廊下にお母様が立っていらして・・・・」 ![]()
![]()
![]()
それを聞いた後、私はとても気味が悪くなってしまい仏壇が怖くなってしまいました。
それ以来、祖母の姿をこの目で見ることはありませんでした。しかし、
なにか困っていることがあったり、心が憂鬱で仕方のない時などそんな時に限って
私は祖母と夢の中で会いました。![]()
![]()
後年、母に聞くと、私は大勢いる孫の中でも特に可愛がられていたそうです。![]()
これは、いい大人になった今でも親戚の叔母からいまだに言われます。
祖母が病気がちだったため、祖母と一緒に写った写真は残念ながら一枚も![]()
ありませんが・・・。 ![]()
![]()
![]()
祖母に背負われ子守り歌を聞いていた心地良い祖母の背中のぬくもりを
私は、今でも鮮明に思い出すことができるのです。
それではまたおあいできますように・・・。

![]()
妖精の部屋の他のストーリーの扉は、下のふくろうをクリックしてね。
![]()
Copyright(C), 1998-2009 Yuki.
禁・物語の無断転載