![]() ゆうが語る、フォークロア
ゆうが語る、フォークロア![]()

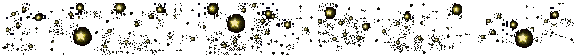
これは数年前、私が珍しく38度の熱を出して寝込んでいた時に体験したことです。
平熱が35度そこそこの私にとって、これは大変苦しいものでした。医者でもらった
頓服薬もまったく効かず、私は仕事もキャンセルして寝ていました。
熱を出して3日目のこと・・・。夜の7時半頃のことです。私は熱を測ろうと思って、
目をつぶったまま枕元においてある体温計を手探りで取ろうと手を伸ばしました。
すると、私の手に触れたのは体温計ではなく温かい人の足でした。「・・・・?」
目を開けて手に触れたものを見ると・・。
それは正座して座っている亡くなった母の下半身でした。![]()
見覚えのあるスカートをはいた、母の腰から下だけの姿だったのです。
そして、腕だけが私の髪を優しくなでるように私の頬の辺りに見えました。
「おかあさん・・・」私は母に話し掛けながらふっくらとしたその手にそっと触れました。
母の手を握った私は何故かとても心が安らいで、熱があるのにもかかわらず大変
気持ち良く、このまま眠ってしまいたいとも思いましたが、もし眠ってしまったら再び母の
姿を見ることはできないだろうと思い、どうしたものだろうかとしばらく考えていました。
そうしているうちに、ふとまったく馬鹿げた考えが浮かんだのです。![]()
『自分が身体から抜けて魂だけになってしまえばお母さんにあえる・・・。』
それに熱があるのだから、そうした条件は整っているような気がしました。
母の手を握りながら目をつぶった私は、たちまちなにか吸い込まれるような感覚の中で
意識だけがひょいと身体から抜けたような気がしたと思ったら、
私は枕元に立っていたのです。
同時にさっきまでの熱の苦しみが嘘のように楽になっていました。![]()
私は鏡に自分を映してみましたが、鏡に自分の姿は映ってはいませんでした。
さらに自分の手を調べてみると、私の手は白い光のようなもので覆われているのが
わかりました。
「おかあさん?」私は母を呼びながらリビングまで歩いていき、母を探しました。![]()
すると、キッチンに母が見慣れない中年の白衣を着た男性を伴って座っていました。
この人は、どなた?私が母に尋ねると、母はにこにこして答えました。
「ゆきちゃんがなかなか良くならないから、こっちでやっと探して来てもらったのに
どうにもならなくて困っていたんだよ」
母の声は、「聞こえる」というよりも、私の心に響いてくるような感じです。
私が戸惑っていると、いいから診てもらいなさいというように母が私をその男性に
娘なんですよと言いながら、紹介しているのには笑ってしまいました。
その人は、この人は生きている人だからなぁ・・と言いながら
持ってきた黒いかばんの中から細い注射器を取り出して私の腕に注射をしたのです。
それは、あっという間でした。
死人から食べ物をもらう夢は良くないことの前触れだと言うが、これはどうなんだろう・・
呆然としてそんなことを考えているうちに、
私はひどく咽喉が渇いているのに気がつきました。テーブルの上の飲みかけの
アイスコーヒーを手に取ろうとしましたがコップがつかめません。
それを見ていた母は私に、もう帰るからと言って目の前から消えてしまいました。![]()
私はどうにも仕様がなく、自分はまだ生きているのだから自分の身体から出たものは
元に戻れるだろうと思っているうちに意識を失いました。
気がつくと再び布団の中でした。
随分時間が経ったようでしたが、ほんの5分ほどの出来事でした。
そして、さっきまでの熱が嘘のように引いてからだが楽になっていたのです。
翌日から私は起きられました。
あの、母が連れてきた男性のお医者さんについて、その後ずっと考えていましたが
やっと思い出しました。実家の近くにある医院のお医者さんで、私が幼い頃何回か診て
もらったことのある人だったことを。
そのお医者さんは心臓麻痺で随分前に亡くなったことも聞きました。
たとえ夢であれ、亡くなっても私を気にかけてくれていた母の愛情を胸に感じます。
それではまたおあいしましょう・・・。

さて、ここで皆さんにも一休みして頂きましょう。 ![]()
私がここでお話するのは、「幽霊」を初めて見た時のことです。思えば、これが私の
あの世の人々に対する価値観を作ったともいえる、いわゆる「原体験」なわけですから、
その体験はある意味ではとても幸せだったのかも知れません。![]()
![]()
今でもはっきりと覚えていますが、それは、私が3歳になる数日前のことでした。![]()
私の記憶は、悲しんでいる母に連れていかれた、母の実家から始まります。
開け放たれた玄関を入ると部屋の中は沢山の花であふれていました。
部屋の隅には箱があり、いろいろな人がかわるがわるその箱を覗いては泣いています。
誰かが、おばあちゃんが死んじゃったと言っています。![]()
人の死を理解するのには、あまりにも幼かった私はその意味が分かりません。
私が母にどうして泣いているの?と聞くと母は、おばあちゃんがいなくなっちゃった・・
というのです。私は不思議でした。 ![]()
![]()
不思議という言葉を当時は知らなかったと思いますが、だって部屋の中には、![]()
ちゃんとおばあちゃんが座ってにこにこ笑っていたからです。
棺の中の祖母は確かに目をつむって寝ています。
しかし、祖母は私に優しい笑顔をむけて、ちゃんとそこに座っているのに・・
誰も祖母の方を見ようとはしないのが不思議でした。 ![]()
そして私は・・・「あそこにおばあちゃんがいる」と言って叱られた記憶があります。![]()
祖母はその後、私が小学校の4年生になるまで、母の実家に遊びに行くたびに
笑顔で迎えてくれました。ある時、法事の席で叔母が青ざめた顔で親戚の人に
小さな声で話しているのを聞きました。
「廊下にお母様が立っていらして・・・・」 ![]()
![]()
![]()
それを聞いた後、私はとても気味が悪くなってしまい仏壇が怖くなってしまいました。
それ以来、祖母の姿をこの目で見ることはありませんでした。しかし、
なにか困っていることがあったり、心が憂鬱で仕方のない時などそんな時に限って
私は祖母と夢の中で会いました。![]()
![]()
後年、母に聞くと、私は大勢いる孫の中でも特に可愛がられていたそうです。![]()
これは、いい大人になった今でも親戚の叔母からいまだに言われます。
祖母が病気がちだったため、祖母と一緒に写った写真は残念ながら一枚も
ありませんが・・・。 ![]()
![]()
![]()
祖母に背負われ子守り歌を聞いていた心地良い祖母の背中のぬくもりを
私は、今でも鮮明に思い出すことができるのです。
それではまたおあいできますように・・・。

![]()
![]()
その日、仕事が早く終わった私は久しぶりに12時過ぎに床に就くことができました。
翌日も朝から予定があったので早く眠りたかったのですが、なかなか寝付くことができず
何度も寝返りを打っているうちに時計は午前1時をまわってしまいました。
ふと気がつくと、真っ暗な筈の部屋の中がぼうっと光っています。![]()
時計を見ようとして枕元を見ると・・・人型の影がゆらゆらと揺れています。
私は起きて部屋の電気を点けましたが、異常はありません。気を取り直し、
また部屋を暗くして布団に入ると部屋の中に白い人型が揺れているのです。
その人型は、盛んに手を動かして、まるで私を招いているかのように見えました。
再び起きて電気を点けましたが、やはり何も見えません・・・。![]()
結局、電気を点けたり消したりを繰り返しすこと5回・・
暗闇の部屋で揺れる人影を眺めながら、ここにいたって私はやっと、
家族の誰かに何か異常が起きたのかと少々不安になりました。
時計は、既に午前2時を回っていました。![]()
実家に電話をするにしてもあまりにも遅い時間ですし、何かが起こっていたとしても
こんな時間ではもう間に合わないなと思い、ともかく寝てしまうことに決めました。
人型は相変わらず、部屋の中で揺れています。
それを眺めつつ、私は眠りに落ちていきました。 ![]()
![]()
その日の朝・・まだやっと夜が明けたばかりの午前5時半、
私は実家からの電話で起こされました。![]()
それは、義理の従兄が昨晩交通事故で死んだという知らせだったのです。
会社を経営している従兄は仕事で遅くなり、帰宅途中に一本道で電柱に
ぶつかり、即死だったこと。![]()
![]()
![]()
警察の調査で死亡推定時刻は午前一時半前後ということでした。![]()
梅雨に入ったばかりの、6月の雨の日の出来事でした。![]()
![]()
それではまたおあいできますように・・・。

![]()
ここからは前回のお話の後日談です。

私には年の離れた妹が一人いますが、この話は妹からきいたものです。
妹は当時小学生で、そもそも私の体験など知る由もありません。
私自身、自分の体験などはめったに人に話すことはありませんし、
その性格ゆえ、大概のことは自分一人の胸にしまっておくという習性があります。
さて、その話とは・・・。
友人の幼なじみの葬儀があった数日後の夕飯の時、妹が一生懸命に両親に
「お化けを見ちゃった」話をしています。母は妹の話を熱心に聞いていましたが、
私は大して気にも留めず聞くとはなしにきいておりました。
妹は興奮していたようです。
授業中に、窓際の生徒が表を指して突然「あっ、お化けだ!」と叫びます。

その声につられて、生徒が先生の制止の声も聞かず窓際に集まりました。
妹の教室は校舎の2階にあって、学校と道路を挟んで執り行なっている
葬儀の様子が丸見えだったのです。
その葬儀をしている家の玄関の前で、白い人型がゆらゆらと揺れ、玄関から出た
り入ったりするのを先生とその場に殺到した生徒が全員見たそうです。
授業中ということもあり、この「事件」は後で問題になり担任の先生からきつく口外
しないようにと言い含められたにもかかわらず、
子供たちの口から口へ伝えられていくことになりました。
いわゆる「都市伝説」として、語られていく話の源になっていく典型だと思います。
それはともかく、その話を聞いていた私は、その家こそお線香をあげに行った家
なのでかなり複雑な思いでした。

私は、無念の思いで旅立たなければならなかったであろう故人を思った時、
それがたとえ事実であっても、死者を見送る儀式に起きた出来事を単なる好奇心
から、騒いで欲しくはありませんでした。
しかし、ここで何かを話せば、それが新
たな真実であるかのように脚色されて「怪談」として語られていくことは
火を見るよりも明らかでしたので私は黙っていました。
この点に関しては、私はたぶん、かなり頑固です。
「死」だけを切り取り怪談や怖い話しとして語ることは、
時には面白い余興でもあるのは私も知っています。ですから、聞き手に回っても、
自分のいろいろな体験を率先して話すということは今まであまりありませんでした
では、何故、今なのか・・・。
おそらく、それはここ数年に起きたいろいろな事件のせいかも知れません。
神の名を騙り、死者の尊厳を冒涜し、あるいは残された人を惑わす一部の人々。
人の死は特別なことではなく誰にでも訪れる平等な現象です。
私は人の心をもてあそぶような一部の人々が、いつか思い違いに気がついて
くれればどんなに幸せだろうと思うのです。
実際、その手の人に被害を受けた人を知っていますが
お金をいくら積んでも心の平安は得られないということがわかります。
心の問題は、心でしか解決できないということを
私のつたない経験から知って欲しい・・そう思ったのです。

まず、死は恐れるものでも避けられるものでもないことを知った時から
いかに生きていくかということが、私の根っこの部分になりました。
それを教えてくれたのは、
もちろん、私の亡くなった母であることに変わりはありません。
それではまた、おめにかかれますように。

![]()
![]()
これは、少し古い話です。
母の日を間近にしたその日の午後、、![]()
![]()
私と友人のAはいつも行く喫茶店であんみつを食べていました。
その後、彼女は幼なじみの隣の家のお兄さんとドライブに行く約束をしてい、
私は言わば時間潰しに呼び出されたというわけです。![]()
しかし、それはそれで楽しい一時を過ごした後、私たちは別れました。
その夜・・・・。彼女からの電話に私は愕然としました。![]()
![]()
![]()
なんと、彼女の幼なじみが交通事故で即死したというのです。
彼女の話によると、いつも時間に正確な人なのに連絡もなくどうしたかと思い、家で
待っているうちに夜になってしまい、届いたのは悲しい事故の知らせだったのです。
残されたのは、母の日のプレゼントの包みがひとつ。無傷だったそうです。
私はその人とは一度しかあったことがなく面識がないのも同様でしたが葬儀の夜、
彼女を慰める為に彼女の家の隣にあるその家へ伺いお線香を上げに行きました。
告別式もとっくに終わり、その家には留守番をかってでた彼女一人でした。![]()
用があると言う彼女に頼まれて、私は初めて来た家で一時間ほど![]()
遺骨の番をすることになってしまい困惑してしまいました。
なにしろ、挨拶をたった一回しか交わしたことのない相手です。さすがに、、![]()
![]()
若かった私は居心地の悪い思いで、遺骨と向き合っていました。
それから半年ほど経ったある日の真夜中のこと・・・。 ![]()
![]()
![]()
ベッドで寝ていた私は強い力で揺り起こされました。
半分寝ぼけながら、母に起こされたのかと思い時計を見るとまだ午前4時前です。
少し腹を立ててもう一度眠ろうとすると、また、背中を強く叩かれました。
今度ははっきり目が覚めて身体を起こすと・・。 ![]()
![]()
ベッドの傍に亡くなったAの幼なじみと見たことのない女性が立っていました。![]()
その時、私はかなり驚いていたと思います。思わず、
「こんばんは、お元気でしたか?」![]()
![]()
なんて間抜けなことを言ってしまったのですから・・。![]() というよりも、
というよりも、![]()
その人のことを良く知らなかった私は、どうしていいか分からなかったのです。
彼は私の問いかけに答えるではなく話し始めました。![]()
![]()
「人生とは空しいもので・・・・」彼の話し続きます。![]()
そして、最後に私に訪ねました。「Aちゃんは、どうしていますか?」
再び眠くなっていた私は、ふとんをかぶりながら答えました。
「幸せに暮らしているから、心配しないでね」なんとも、今、こうして思い出しても
もっと言い様があったのではないかと少し心が痛みますが、![]()
![]()
![]()
なにしろ、もう、面倒になっていたのです。相手が幽霊だというのも頭にありました。
彼の目線は何処か遠くにあって、私を見ているようで見ていないのです。![]()
私は自分がもしかして、まだ寝ぼけているのかなと思い始めていましたし、
会話するのがなんか、馬鹿馬鹿しくなってきてたのでした。![]()
それで、突き放すような態度になってしまったのです。
彼が言うには、ずっと彼女を見守ってきたのだが、声をかけても気がついてくれない。
そこで、仲の良い私のところに来て、自分が今もこうして生きていることを![]()
彼女に伝えて欲しいと思ってこうして来た、、ということでした。
私は彼にあなたはもう、死んでいるんですよ・・・。言いたいことはわかったから
さようなら。そう言い放って、布団をかぶって眠ってしまいました。
翌日・・・。私は考えた末、自分の体験を彼女に話しました。![]()
![]()
話をしているうちに彼女は大きな目に涙を浮かべてうなずいていました。
実は、話の内容に、彼女と彼しか知らないことがあったのです。
それをここに書くことはできませんが、それは、彼女の心に響いたと思います。
今、Aは幸せに暮らしています。恐らく、、幼なじみの彼のことも ![]()
忙しい日常の生活の中で、遠い日の記憶でしかなくなっていることでしょう。
今も彼女を見守っているかもしれない彼のために、、
あえて、私はここに彼と出遭ったあの夜のことを書いてみることにしました。
この話しには後日談がありますが、それは、いずれまた・・・。
![]() それでは、また明日の晩お目にかかりましょう。
それでは、また明日の晩お目にかかりましょう。
おやすみなさい。

![]()
![]()
妖精の部屋の他のストーリーの扉は、下のふくろうをクリックしてね。
![]()
Copyright(C), 1998-2009 Yuki.
禁・物語の無断転載