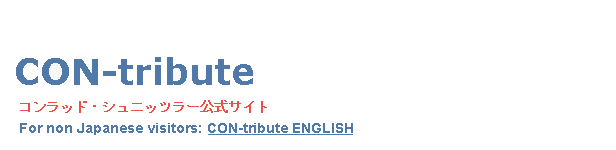
ときに夢は現実となることがあります ― 時間はそれなりに掛かったとしても。コンラッド・シュニッツラーの夢の中心には「すべての人はアーティストである」といった信念があります。これは、単に、すべての人にアーティストの才能があることを意味しているのではありません。アートをプロデュースして、なおかつそれを配給する手段は、誰にでも手の届く範囲にあるべきで、限られた人の特権であってはならないのです。コンラッド・シュニッツラーが初期の頃に関わっていた音楽プロジェクト(Geraeusche、Human Being、Kluster) は、集団での即興にこだわったもので、手の届く範囲にある物品は、すべて音楽のための楽器として使われました。シュニッツラーは常に低予算でやっていて、レコードを自主制作したり、カセットで自分の音楽を配給し始めた最初の一人でした。収入が入っても、彼は規模を拡大して採算に見合うだけの部数を売るようなことはせず、代わりに、新しいプロジェクトにつぎ込んでいました。PCやインターネットの出現が、世界的なムーブメントの火付け役になったことについても同じことがいえます。未だに数百万人の人々がこの技術を利用していないわけですが、あらゆる人々があらゆる人々のために音楽、映像、文学をプロデュースするための方法が、ここには存在しています。ただ単に、これらの道具を平等に用いる機会が社会に欠けているだけです。
アドルノは書きました。「アートがすべきことは、カオスを秩序の中に持ち込むことである」と。1968年にシュニッツラーとKlusterの仲間が設立した「ツォディアック・フリー・アーツ・ラボ(Zodiak Free Arts Lab)」で行われたことは正にそういうことです。古いルールをなくす。簡単なようでいて、なかなかそうはいきません。新しいアイデアというものは、古い社会から生まれた子供のようなものです。それらはただ、古い社会という壁にヒビを入れるだけですが、その隙間から差し込む光は新しい世界を約束してくれます。日常生活の中でデスクや工場の組み立てラインにいる(または生産活動や利益といったものから全くかけ離れた)人々をアートに転向させることは、壁にそのようなヒビを入れる行為に相当します。これは、シュニッツラーがヨーゼフ・ボイスと時間を共にしたときに得た主要な考え方です。シュニッツラーがデュッセルドルフでアートを学ぶことができたこと自体、その考えの一部といえます。彼は高い学歴を持てるような特権ある環境に育ったわけではありません。彼はドロップアウトする前は工場労働者でしたが、揺りかごから墓場までのレールが社会によって引かれていて、自分の裁量で決められる部分はほとんどありませんでした。過去の大戦の最中、彼のように経済弱者で、政権に居座る独裁主義の枠組みに沿えないドイツ人は、限られた選択肢の中から選ぶしかありませんでした。ホームレスになるか、他国の外国人部隊に入隊するか、船乗りになるかです。シュニッツラーは迷うことなく船乗りを選びました。デュッセルドルフに戻ると、彼はボイスに出会いました。ボイスは60年代に、正統な教育がなくても才能があれば誰でも講義が受講できるよう、クラスを開放していました。デュッセルドルフが位置するドイツのノルトライン・ウェストファーレン州では、60年代に、労働者の活動によって支持されたドイツ社会民主党(SPD)が行政を担っていました。階級、性別、経済力に関係なく、あらゆる人々に教育を、というのが活動目的の一つでした。だから、拍手喝采でボイスの考えを支持するものと当然思われるでしょう。いいえ、彼はその後、解職されたのです。
1966年にコンラッド・シュニッツラーはベルリンに移り住み、絵画や彫刻から音楽へと切り替えました。音楽は、突然本能的に沸き起こる創造性や、「アートは美術館だけのものであってはならない」というフルクサス運動の考えに、より適した場であるようにみえました。ツォディアック・フリー・アーツ・ラボでは、最初に3種類の音楽活動からなる融合がありました。それぞれ違う方面から来たものですが、社会の流れにより同調、集束したそれらの活動とは、フリージャズ、サイケデリック・ロック、もう一つはベリオやノーノ、シュトックハウゼンがやっていた現代音楽でした。これらはすべて同時期にやって来たわけですが、共通した信念がありました。それは、先の二つの世界大戦において、古い社会が醜い側面をさらし、その後遺症が残る中で、今こそ新しい社会が必要で、新しい社会には新しい音楽や新しい形態のアートが必要である、といったものです。この極めて希な瞬間は長くは続きませんでした。もしも一瞬でも一枚岩となったときがあったとしたら、それらはすぐにまたバラバラになったと言えます。ジャズ・ミュージシャンは、彼等のステータスや聴衆が確保できるジャズ本来の場に戻り、ロック・ミュージシャンは、沢山のファンから一段せり上がったステージの上でスポットライトを浴び、スターでいられることを愛しました。そして、クラシックの音楽家は、オペラハウスへと戻っていきました。ブーレーズは「オペラ座を爆破せよ」と息巻いていましたが、今ではオペラの監督の座についています。集団は分裂しました。シュニッツラーはその後も一人で自分の道を歩み続けましたが、そこには数え切れない程の協力がありました。彼はどこかで妥協しなければなりませんでしたが、それは同時に、周囲も妥協に応じなければならないことを意味します。このような問題は、本人や周りの人々が、その活動を信じたときから始まっています。彼は初めから妥協を目的とすべきでした。
シュニッツラーは、エレクトロニック・ミュージックの重要人物の一人だと常に言われますが、音楽を始めた頃は、電子楽器などありませんでした。誰もそのようなものを買う余裕はありませんでした。楽器として使っていた物と言えば、日用品や壊れた楽器、他のミュージシャンが捨てた物でした。新しい音楽は、ほとんどの場合、ルールを破って、本来とは違うやり方で楽器を用いたときに生まれます。エレクトロニクス(最初は研究所や無線室の余り物)の使用が増えてきた理由は、少年が新しいオモチャに惹かれるのとは違います。そこには、日常生活では決して耳にすることのない音の魅力がありました。初期の電子音楽がSF映画に取り入れられたのも偶然ではありません。未来の映像とサウンド。50~60年代は楽観的な時代で、科学技術の進歩が飢えや貧困を過去のものとし、そのうち、退屈で時間の掛かる労働から人類が開放される日が来るだろうと考えられていました。このような雰囲気の中では、電子音楽とアコースティック音楽を比べる議論はあまり意味がありません。大多数の人々は新しい可能性の方に感化されていました。コンサート・ホールではステージにテープ・レコーダーが置かれ、ハービー・ハンコックやマイルズ・デイビスは伝統的なジャズを離れて電子楽器を使うようになりました。ミック・ジャガーでさえ、ムーグのシンセサイザーを自分の手で試してみたほどです。クラフトワークは「ホンモノらしさ」を求めることを笑い飛ばしました。「ホンモノらしさ」とは、ロック・ミュージシャンが肉体労働者のように激しく動き回り、汗まみれになることこそがホンモノだという考えです。クラフトワークは、自分たちにそっくりなロボットを作って、ツアーのときにパフォーマンスをさせて観客にインパクトを与えました。
シュニッツラーはさらに上を行きます。多分、あなたが彼と同じ結論に達するためには、まずは画家から始めるべきでしょう。絵画を見るとき、普通、画家に会おうという発想はないでしょうし、絵を描いているときに画家の肩越しに見るようなことも考えないでしょう。カセット・コンサートのコンセプトでもって、彼は、音楽を演じるときに本人がその場にいる必要はないことに気付きました。彼は曲を構成するブロックに相当するものをテープに録音していきます。パフォーマー(シュニッツラー本人である必要はありません。)は、次々に数が増えていくテープの中から好きなものを選ぶことができ、(今はテープからCDに変わったので、扱いが楽で音質もよくなりましたが)それらを自由にミックスできるわけです。シュニッツラーは作曲家で、パフォーマンスをするアーティストは、かなり自由度の高い指揮者と言えます。シュニッツラーは自分自身でもこのテクニックを用いています。彼は音楽を狭い範囲で縦に発展させるようなことはせず、出だしからある種のフィナーレ、あるいは約束された至福のときまで、一貫してコンセプトにしたがう形で行います。その音楽は、どの方向にも進むことができ、また、あらゆる可能性が探求できるよう、自由に横へ広がる形で創られていきます。それこそが自由と呼ぶにふさわしいものです。
原文(英語):Con-tributed article from Wolfgang "Sequenza" Seidel (16.4.06)
[ CON-tribute JAPANESE ] [ CON-tribute ENGLISH ]
Copyright © 2005-2026 CON-tribute All Rights Reserved.
当サイトで掲載している文章や画像などを無断転載、複製(コピー)することを禁止します。
※詳細はこちら: 著作権・当サイトへのリンク・免責事項・プライバシーポリシー